親知らずは抜かなくても大丈夫?抜かないメリットとデメリットを解説
「親知らず」と聞くと、「抜かないといけないもの」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、親知らずは必ずしも抜歯が必要なわけではなく、その状態や生え方によっては経過観察という選択肢が可能なケースもあります。今回は、親知らずを抜かずに残す場合について、そのメリットとデメリット、抜歯の判断基準について詳しく解説します。
1. 親知らずを抜かない選択肢とは?

親知らずは、第三大臼歯とも呼ばれる奥歯のことで、一般的には17歳から25歳頃に生えてきます。しかし、現代人の顎は昔に比べて小さくなっているため、スペースが足りずに親知らずがうまく生えないことが増えています。そのため、以下のような生え方や状態によっては、「抜かずに様子を見る」という判断がされるケースもあります。
①正常に生えている場合
親知らずが真っ直ぐ生えていて噛み合わせにも問題がない場合は、抜歯せずに経過観察することもあります。しっかり噛める状態であれば、機能的にも役立つ可能性があります。
➁骨や神経に近い場合
親知らずの根が顎の骨や下顎神経に近接している場合、神経麻痺や骨折といった抜歯によるリスクが高くなる可能性があります。この場合、歯科医師が抜かずに経過を観察することを推奨するケースもあります。
➂高齢者の場合
年齢が高くなると、抜歯後の回復が遅くなったり、全身疾患の影響を受けやすくなったりすることがあります。そのため、高齢の方では無理に抜歯を行わず、炎症リスクが低い限りは残す選択肢が取られることがあります。
④持病がある場合
糖尿病や心臓病など持病を抱えている場合、手術による全身への負担を避けるために、抜歯せず経過観察を選ぶこともあります。
⑤将来の移植用に残す場合
何らかの事情で他の歯を失ったときに、親知らずを移植歯として活用できる可能性があります。このように、将来に備えて親知らずを保存する場合もあります。
以上のように、親知らずを抜かない選択肢は、患者さん一人ひとりの口腔内の状況や全身状態に応じて慎重に判断されます。
2. 親知らずを抜かないことで得られるメリット

以下に、親知らずを抜かずに残すことで得られる主なメリットを解説します。
①手術によるリスク回避
親知らず抜歯の難易度が高い場合、神経損傷や大きな腫れ、感染症などのリスクを伴うことがあります。抜歯を回避することで、これらのリスクを避けることにつながります。
➁自然な噛み合わせの維持
親知らずが問題なく生えている場合、上下の噛み合わせが保たれ、噛む力をバランスよく分散させることができます。これにより、他の歯への負担を減らせる可能性があります。
➂移植歯として活用できる可能性
前述したように、将来、別の歯を失った場合に親知らずを移植する「自家歯牙移植」という選択肢が取れる可能性があります。そのため、親知らずを健康な状態で保存しておくことには、大きな意味があるといえるでしょう。
④費用や通院の負担が少ない
親知らずの抜歯には、手術費用や術後の通院・処置が必要です。抜かずに済む場合、これらの費用や通院による身体的・精神的な負担を避けられる可能性があります。
⑤骨や神経を守れる
特に下顎の親知らずの場合、抜歯時に下歯槽神経を傷つけるリスクがあります。抜かずに済めば、大切な神経や骨を守ることにつながります。
このように、親知らずを抜かないことで得られるメリットは、手術リスクを回避するだけでなく、将来的な治療の選択肢が広がる可能性もあります。
3. 親知らずを抜かないときに注意すべきデメリット
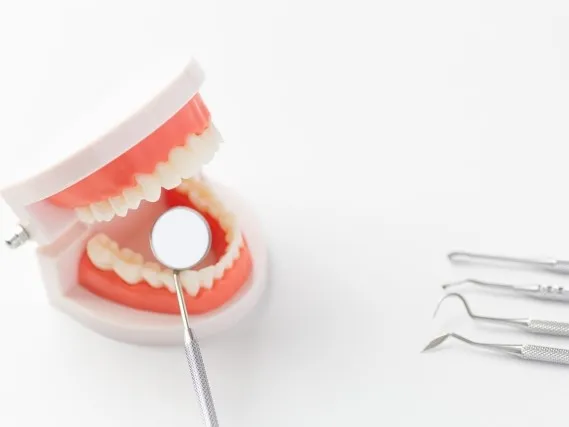
親知らずを抜かない選択肢にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。抜かずに様子を見る場合の主なデメリットを解説します。
①むし歯や歯周病のリスクが高まることがある
親知らずは奥に位置するため、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすい環境にあります。そのため、むし歯や歯周病を発症する可能性が高まります。場合によっては、隣接する第二大臼歯にも悪影響を及ぼすことがあり、健康な歯まで失う恐れがあります。
➁周囲の歯並びへ悪影響の可能性も
親知らずが少しでも斜めに生えていたり、わずかに押す力が加わるだけでも、隣の歯を圧迫し、歯並び全体に影響を及ぼすことがあります。これにより、噛み合わせの乱れや、矯正治療が必要になる場合もあります。
➂炎症を引き起こすことがある
親知らずの周囲に汚れが溜まり、歯ぐきが炎症を起こすと、腫れや痛みが出たり膿が溜まったりする「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」になることがあります。ひどい場合には、口が開かなくなったり、発熱を伴ったりするケースもあります。
④顎関節への負担につながるケースも
不適切な親知らずの位置は、噛み合わせに影響を与え、顎関節に余計な負担をかけることがあります。これが原因で、顎関節症を引き起こすケースも報告されています。
⑤口臭や不快感が生じることがある
親知らず周辺は清掃が難しく、細菌が繁殖しやすい環境です。これにより口臭や口腔内の不快感が生じることもあり、日常生活に支障をきたす可能性があります。
抜かない選択肢を取る場合には、これらのリスクを十分に理解し、歯医者の定期検診で状態を確認することが非常に重要です。
4. 親知らずを抜く・抜かないを決めるポイント

親知らずを抜くか抜かないかの判断は、自分自身だけで決めるものではなく、歯科医師と相談して慎重に決定する必要があります。以下に、判断の目安となるポイントを解説します。
①親知らずの生え方と位置
レントゲン撮影によって、親知らずの角度や周囲の組織との関係を確認します。真っ直ぐ生えていて噛み合わせに問題がなければ、抜かずに経過観察が可能な場合もあります。
➁症状の有無
腫れや痛み、違和感などの症状がある場合は、抜歯が検討されることがあります。また、症状がない場合でも、将来的なリスクを考慮して判断されるケースもあります。
➂年齢と健康状態
若いうちは抜歯後の回復が早く、手術リスクも低いとされています。一方、年齢が上がると骨が硬くなり、抜歯のリスクも高まりやすくなるため、早めの判断が求められることもあります。
④神経や骨への影響リスク
親知らずが神経や骨に接近している場合、抜歯手術による合併症リスクが高まる可能性があります。このようなケースでは、無理に抜かず、定期的な経過観察を行うことが推奨される場合もあります。
⑤口腔内の衛生状況
親知らず周囲の清掃が難しい場合、むし歯や歯周病のリスクが高まりやすく、そのため抜歯を検討することが望ましいケースもあります。逆に、清掃が十分に行われている場合は、残す選択肢が考慮される可能性もあります。
⑥歯科医師の総合判断
これらすべての情報を総合的に見たうえで、歯科医師が患者さんにとって最適な選択を提案します。自己判断で放置することは避け、必ず歯科医師の診断を仰ぎましょう。
親知らずは、個々の状況によって最適な対応が異なります。抜くか抜かないかで迷った場合は、早めに歯科医院を受診することが大切です。
5. 名古屋市南区の歯医者 やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療

名古屋市南区の歯医者「やくし歯科・矯正歯科」では、一人ひとりの状態に寄り添い、将来を見据えた治療をご提案しています。
親知らずに関するご相談・診断・抜歯治療も幅広く対応しており、他院紹介や外部医師の派遣ではなく、口腔外科の専門知識を持つ院内医師が対応します。
日々様々な症例に向き合い、丁寧で安心できる診療を心がけています。
また、診断の精度や治療の安全性向上のため、医療機器の導入も積極的に行い、小さなお子さま連れの方でも通いやすいように託児サービスも行っています。
<やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療>
①的確な診断と分かりやすい説明
親知らずは斜めや横向きに生えているケースも多く、抜歯が必要かどうかを見極めるには正確な診断が不可欠です。当院では、高精度なCTやデジタルレントゲンを使用し、親知らずと周囲の神経や血管との位置関係を立体的に把握し、撮影した画像を使いながら、患者さんに分かりやすく丁寧にご説明します。
➁痛みや不安に配慮した麻酔法
抜歯が必要な場合には、局所麻酔や笑気麻酔に加え、眠ったような状態で抜歯治療を行う静脈内鎮静法が選択できます。
➂「抜かない」という選択肢も
すべての親知らずを抜歯する必要があるわけではありません。まっすぐに生えていて問題がなければ、無理に抜歯せず定期的な経過観察を行うケースもあります。患者さんの将来の健康やライフスタイルを考慮し、柔軟な対応を心がけています。
親知らずの治療は、単に「抜く・抜かない」の判断だけではなく、将来の健康を見据えたトータルな視点が必要です。
まとめ
親知らずは必ずしも抜く必要があるわけではなく、個々の状態に応じた判断が求められます。抜かずに残すことで得られるメリットがある一方、むし歯や歯並びへの悪影響といったデメリットも存在します。歯科医師による正確な診断を受けたうえで、最適な選択をすることが重要です。
名古屋市南区で親知らずの抜歯についてお悩みの方は、やくし歯科・矯正歯科までお問い合わせください。
監修:やくし歯科・矯正歯科 院長 鬼頭 広章
所属学会
国際インプラント学会 ICOI Fellow
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯周病学会 会員
日本顎咬合学会 会員
日本デジタル矯正歯科学会 会員
日本臨床歯科学会 SJCD 会員
MID-G 理事
名古屋臨床咬合研究会 NOAH 理事
K-Project 会員
取得資格
USC(南カリフォルニア大学)JAPANProgram 卒業 東京SJCDレギュラーコース修了
OSG(矯正アレキサンダータイポドントコース)修了
ITIインプラントコース ベーシック、アドバンス修了
エキスパートハンズオンCAMLOGコース修了
NOBEL BIOCAREサティフィケート多数取得
インビザライン矯正 ベーシックコース修了
5D アドバンスコース修了
2017年 MID-Gレギュラーコース、マニュアルコース受講
矯正LASコース受講
歯周形成外科マイクロアドバンスコース受講
CSTPC受講
2021年 ODGC (矯正診断コース)修了
アライナーオルソドンティクス6デイズコース
明海大学国際インプラント学会認定コース
ハーバード大学歯学部日本CEコース
認定医
日本デジタル矯正歯科学会
日本顎咬合学会

 052-811-1340
052-811-1340