親知らず抜歯時は局所麻酔?全身麻酔?麻酔法の違いを解説
親知らずの抜歯にあたっては、どの麻酔方法を選ぶかも大きなポイントになります。局所麻酔や全身麻酔などの麻酔法を聞いたことがある方も多いかもしれません。麻酔の方法によって、抜歯中の痛みや意識の有無、術後の体調などにも違いが出てくるため、正しい知識を持ったうえで選択することが大切です。今回は、親知らずの抜歯に使われる麻酔の種類や、局所麻酔と全身麻酔の基本的な違い、さらにそれぞれの麻酔による治療の流れについて詳しく解説していきます。
1. 親知らずの抜歯に使う麻酔とは
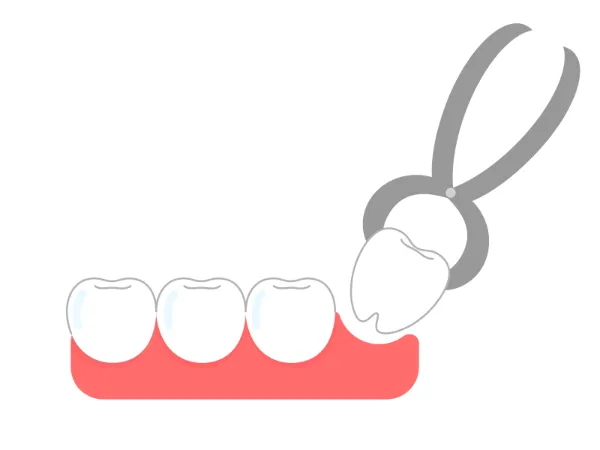
親知らずの抜歯には、痛みを抑えるために麻酔が欠かせません。使われる主な麻酔方法には、局所麻酔と全身麻酔の2種類があります。
①【局所麻酔】
局所麻酔は、抜歯する部分のみに麻酔薬を注射して感覚を麻痺させる方法です。意識ははっきりしており、会話も可能です。一般的なむし歯治療や、小規模な手術でも広く使用されています。
②【全身麻酔】
全身麻酔は、麻酔薬を静脈に注射したり、吸入麻酔薬を吸わせたりして、全身の意識を完全に失わせる方法です。手術中の記憶はなく、痛みも感じません。親知らずが複雑に埋まっている場合や、患者さんが強い恐怖心を持っている場合に選択されることがあります。
③【局所麻酔+静脈内鎮静法】
局所麻酔に加え、リラックス効果のある薬剤を静脈から投与する「静脈内鎮静法」という選択肢もあります。意識は浅く保たれますが、ウトウトしている間に処置が進むため、不安を和らげることができます。
④麻酔方法の選択基準
どの麻酔を選ぶかは、親知らずの状態(位置や生え方)、患者さんの希望、不安の程度、既往歴や体調によって決まります。歯科医師との十分な相談が重要です。
患者さん一人ひとりに合った麻酔方法を選ぶことで、抜歯の負担を軽減することが可能です。
2. 局所麻酔と全身麻酔の基本的な違い

局所麻酔と全身麻酔では、効果やリスク、患者さんへの影響に大きな違いがあります。
①【意識の有無】
局所麻酔では意識があり、施術中の音や感覚も多少は感じます。一方、全身麻酔では意識が完全に失われるため、施術中の記憶は一切ありません。
②【体への負担】
局所麻酔は、体への負担が比較的小さく、処置後すぐに帰宅できることがほとんどです。全身麻酔は、麻酔をかけるために入院や長時間の経過観察が必要になる場合があり、体にかかる負担も大きくなります。
③【リスク】
局所麻酔は副作用が少ないですが、まれにアレルギー反応や血圧低下が起こることがあります。全身麻酔は、呼吸抑制や麻酔からの覚醒に時間がかかるリスクがあるため、特に慎重な管理が必要です。
④【コスト】
局所麻酔は保険適用で負担が少ないのに対し、全身麻酔は高額になる場合が多く、別途施設使用料などがかかることもあります。
⑤【選択のポイント】
親知らずの抜歯が比較的簡単で、患者さんに強い恐怖心がない場合は局所麻酔が適しています。一方で、抜歯が難しいケースや、極度の不安を抱える患者さんには全身麻酔が選ばれることもあります。
⑥【歯科医師との相談が重要】
麻酔方法は歯科医師が一方的に決めるものではなく、患者さん自身の希望や体調をふまえて決めるべきです。しっかりと説明を受け、納得したうえで選択しましょう。
3. 麻酔ごとの抜歯中・抜歯後の流れ

麻酔の種類によって、親知らずの抜歯中や抜歯後の流れにも違いが生じます。それぞれの特徴を整理していきましょう。
①【局所麻酔の場合】
・抜歯前に麻酔を施し、感覚がなくなるのを待ちます(通常数分程度)。
・意識ははっきりしており、歯科医師の指示を聞きながら治療を進めます。
・抜歯中は「圧迫される感覚」や「音」は感じることがありますが、痛みはほとんどありません。
・抜歯後はそのまま帰宅でき、普段通りの生活が可能ですが、麻酔が切れるまでは飲食に注意が必要です。
②【全身麻酔の場合】
・事前に健康状態のチェックを行い、絶食指示などを受けます。
・手術室で麻酔をかけ、完全に意識がなくなってから抜歯を開始します。
・術後は麻酔からの回復を待つため、回復室で数時間安静に過ごします。
・全身状態の確認後、問題がなければ帰宅できることもありますが、入院が必要なケースもあります。
③【術後の注意点】
どちらの麻酔方法でも、抜歯後の出血や腫れ、痛みへの対処が必要です。とくに全身麻酔の場合は、術後数日は体調の変化に注意し、無理をせず安静を保つことが勧められます。
④【痛み止めや抗生物質の服用】
歯科医師から処方された痛み止めや抗生物質は、指示通りに服用することが大切です。自己判断で薬を中断すると、感染症や痛みが悪化するリスクがあります。
⑤【経過観察】
局所麻酔の場合も全身麻酔の場合も、抜歯後の経過観察が欠かせません。特に、腫れや痛みが強い場合には、早めに歯科医院へ相談しましょう。
⑥【まとめ】
抜歯中・抜歯後の流れをしっかり理解しておくことで、安心して親知らずの治療に臨むことができます。
4. 自分に合う麻酔の選び方

親知らずの抜歯にあたって、どちらの麻酔が自分に合っているかを選ぶポイントについて解説します。
①【親知らずの生え方で判断】
親知らずがまっすぐ生えていて抜歯が簡単な場合は、局所麻酔で十分です。一方、骨の中に埋まっていたり、周囲の神経や血管に近い場合は、全身麻酔を検討することがあります。
②【不安感や恐怖心の程度で判断】
治療に対して強い恐怖心がある場合は、静脈内鎮静法や全身麻酔を選ぶと良いでしょう。局所麻酔のみでの抜歯は、不安感が大きいと、体にストレスをかけることがあります。
③【持病や体調をふまえて判断】
心臓疾患、呼吸器疾患、過去の麻酔アレルギー歴がある方は、麻酔方法に制限が出ることがあります。歯科医師と十分に相談し、リスクの少ない方法を選びましょう。
④【通院環境やサポート体制で判断】
全身麻酔を選ぶ場合、手術後に送迎が必要となることもあります。家族のサポートや通院のしやすさも考慮して選択することが大切です。
⑤【費用面を考慮する】
局所麻酔に比べ、全身麻酔はコストが高額になる傾向があります。治療費の負担を含め、あらかじめ費用面についても歯科医院で確認しておきましょう。
⑥【最終的には歯科医師と相談】
親知らずの状態や全身の健康状態をふまえ、最適な麻酔方法を提案してもらうことが重要です。疑問点は遠慮せず質問し、納得して治療に臨みましょう。
5. 名古屋市南区の歯医者 やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療

名古屋市南区の歯医者「やくし歯科・矯正歯科」では、一人ひとりの状態に寄り添い、将来を見据えた治療をご提案しています。
親知らずに関するご相談・診断・抜歯治療も幅広く対応しており、他院紹介や外部医師の派遣ではなく、口腔外科の専門知識を持つ院内医師が対応します。
日々様々な症例に向き合い、丁寧で安心できる診療を心がけています。
また、診断の精度や治療の安全性向上のため、医療機器の導入も積極的に行い、小さなお子さま連れの方でも通いやすいように託児サービスも行っています。
<やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療>
①的確な診断と分かりやすい説明
親知らずは斜めや横向きに生えているケースも多く、抜歯が必要かどうかを見極めるには正確な診断が不可欠です。当院では、高精度なCTやデジタルレントゲンを使用し、親知らずと周囲の神経や血管との位置関係を立体的に把握し、撮影した画像を使いながら、患者さんに分かりやすく丁寧にご説明します。
➁痛みや不安に配慮した麻酔法
抜歯が必要な場合には、局所麻酔や笑気麻酔に加え、眠ったような状態で抜歯治療を行う静脈内鎮静法が選択できます。
➂「抜かない」という選択肢も
すべての親知らずを抜歯する必要があるわけではありません。まっすぐに生えていて問題がなければ、無理に抜歯せず定期的な経過観察を行うケースもあります。患者さんの将来の健康やライフスタイルを考慮し、柔軟な対応を心がけています。
親知らずの治療は、単に「抜く・抜かない」の判断だけではなく、将来の健康を見据えたトータルな視点が必要です。
まとめ
親知らずの抜歯では、局所麻酔と全身麻酔のどちらを選ぶかによって、治療中や治療後の負担が大きく変わります。抜歯の難易度、不安感、体調、費用などを総合的に考慮し、歯科医師と十分に相談して、自分に合った麻酔方法を選択することが大切です。
名古屋市南区で親知らずに関するご相談は[やくし歯科・矯正歯科]までご相談ください。安全・丁寧な抜歯治療で、患者さん一人ひとりに合ったサポートを提供しています。
監修:やくし歯科・矯正歯科 院長 鬼頭 広章
所属学会
国際インプラント学会 ICOI Fellow
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯周病学会 会員
日本顎咬合学会 会員
日本デジタル矯正歯科学会 会員
日本臨床歯科学会 SJCD 会員
MID-G 理事
名古屋臨床咬合研究会 NOAH 理事
K-Project 会員
取得資格
USC(南カリフォルニア大学)JAPANProgram 卒業 東京SJCDレギュラーコース修了
OSG(矯正アレキサンダータイポドントコース)修了
ITIインプラントコース ベーシック、アドバンス修了
エキスパートハンズオンCAMLOGコース修了
NOBEL BIOCAREサティフィケート多数取得
インビザライン矯正 ベーシックコース修了
5D アドバンスコース修了
2017年 MID-Gレギュラーコース、マニュアルコース受講
矯正LASコース受講
歯周形成外科マイクロアドバンスコース受講
CSTPC受講
2021年 ODGC (矯正診断コース)修了
アライナーオルソドンティクス6デイズコース
明海大学国際インプラント学会認定コース
ハーバード大学歯学部日本CEコース
認定医
日本デジタル矯正歯科学会
日本顎咬合学会

 052-811-1340
052-811-1340