親知らずは何歳で抜くべき?抜歯の理由や抜歯後の注意点について解説
親知らずは、10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯で、生え方や位置によっては痛みや腫れを引き起こすこともあります。そのままにしておくと、歯並びの悪化やむし歯、歯ぐきの炎症といったトラブルの原因になることも少なくありません。ただ、すべての親知らずを抜く必要があるわけではないため、正しい知識をもとに判断することが重要です。
今回は、親知らずを抜くべき理由や適切な時期、抜歯後の注意点、さらに抜かない選択肢について解説します。
1. 親知らずを抜く必要性とは?抜歯を考える理由を整理
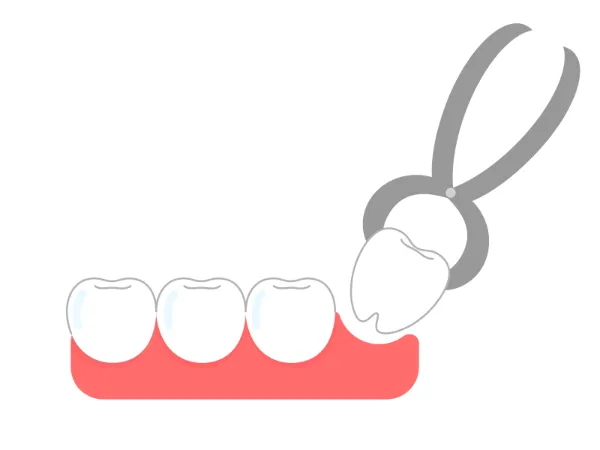
親知らずは「第三大臼歯」とも呼ばれ、最も奥に生えてくる永久歯です。現代人の顎は昔よりも小さくなっているため、親知らずが正常に生えきらずに問題を引き起こすことが増えています。以下に、親知らずの抜歯が推奨される理由を解説します。
①むし歯や歯周病のリスクが高まりやすい
奥にある親知らずは歯ブラシが届きにくく、食べかすや汚れがたまりやすいため、むし歯や歯周病になりやすいです。また、隣の歯にまで影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。
➁歯並びや噛み合わせに影響する可能性がある
横向きや斜めに生えている親知らずは、前の歯を押す力が働き、歯並びを乱すことがあります。また、矯正治療後に歯並びが戻ってしまう「後戻り」の原因になることもあります。
➂智歯周囲炎の原因になることがある
親知らずが一部歯ぐきに覆われたままだと、細菌が侵入しやすくなり、歯ぐきの腫れや痛みを引き起こす「智歯周囲炎」を発症することがあります。智歯周囲炎は再発を繰り返すことが多く、そのため抜歯を提案されることもあります。
④口臭や不快感の原因になることも
汚れが溜まりやすい親知らず周辺では、細菌が繁殖しやすく、口臭や不快な味の原因になることもあります。
⑤顎関節症や頭痛の引き金となることがある
噛み合わせに影響が出ることで顎関節に負担がかかり、慢性的な頭痛や肩こりなど全身の症状につながることもあります。
2. 親知らずはいつ抜くのがよい?何歳で抜くかの目安

親知らずをいつ抜けばよいか、迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。適切な抜歯時期には個人差がありますが、一般的な目安を以下に解説します。
①10代後半から20代前半
この時期は、親知らずの根が完成しきっていないことが多く、骨も柔らかいため抜歯が比較的容易で、回復も早いとされています。顎の成長が終わりかけているタイミングで検討するのが理想的です。
➁症状が出たら年齢を問わず対応が必要
痛み、腫れ、違和感などの症状がある場合は、年齢にかかわらず抜歯を検討する必要があります。放置すると炎症が広がり、周囲の歯や顎の骨にも影響を及ぼすおそれがあります。
➂矯正治療の前に抜くケースもある
歯列矯正を予定している方は、親知らずが歯並びに影響する可能性があるため、事前の抜歯が推奨されることがあります。これは、治療計画の一環として判断されるケースです。
④40代以降はリスクを踏まえ慎重に
年齢が上がるにつれて骨が硬くなり、抜歯後の腫れや痛み、治癒に時間がかかることがあります。また、全身疾患との関係で処置が複雑になる場合もあるため、慎重な判断が必要です。
⑤経過観察も立派な選択肢
すぐに抜く必要がない場合は、レントゲンなどで定期的に経過を観察するという選択肢もあります。抜歯の適切なタイミングを逃さないためには、歯医者の定期検診がカギとなります。
親知らずの抜歯は「今すぐ」ではなくても、将来的なトラブルを未然に防ぐために、計画的に判断することが大切です。
3. 親知らず抜歯後に気をつけたい生活上のポイント

親知らずの抜歯後は、ちょっとした行動が腫れや痛み、感染の原因になることもあるため、注意が必要です。傷口の治癒を妨げないよう、親知らず抜歯後に気をつけるべき生活上のポイントを以下に解説します。
①抜歯当日は安静に過ごすことが大切
血流が増えると出血が止まりにくくなるため、抜歯当日は入浴・運動・飲酒を控え、できるだけ安静に過ごしましょう。特に入浴は、シャワー程度にとどめるのが無難です。
➁食事は柔らかく刺激の少ないものを選ぶ
抜歯当日から翌日は、傷口に負担をかけないように、うどんやおかゆ、ヨーグルトなど柔らかい食事を取りましょう。熱いものや辛いもの、アルコールは避け、患部側で噛むことも控えてください。
➂うがいや歯磨きは慎重に行う
強いうがいや、患部をゴシゴシ磨くことは避けましょう。血が固まりにくくなり、治癒を妨げる「ドライソケット」と呼ばれる状態になることがあります。
④処方された薬は指示通りに服用する
抗生剤や痛み止めが処方された場合は、自己判断で中断せず、歯科医師の指示通りに服用することが回復の近道です。
⑤腫れや内出血があっても慌てない
下の親知らずを抜いた場合などは、頬が腫れたり、内出血で青あざのようになることもありますが、ほとんどは自然に治まります。数日経っても改善しない場合は、早めに受診しましょう。
抜歯後は、治癒を妨げない生活を意識することで、トラブルを最小限に抑えることが期待できます。
4. 抜かない選択肢もある?親知らずの保存判断と経過観察のポイント

親知らずは必ずしも抜かなければならないものではありません。状態によっては、抜歯をせずに経過観察を行うことが適切な場合もあります。以下に、親知らずの保存判断と経過観察のポイントを解説します。
①正常に生えていれば保存可能な場合もある
親知らずがまっすぐに生えており、噛み合わせや周囲の歯に影響がない場合は、必ずしも抜歯の必要はありません。むし歯や歯周病のリスクが少なく、しっかりとブラッシングができていれば、保存する選択肢もあります。
➁将来的なリスクがある場合は慎重に判断
一見問題がなくても、親知らずが歯ぐきに埋まっていたり、隣の歯に接している場合は、将来的にむし歯や炎症を引き起こす可能性があります。症状が出る前に抜いたほうが良いケースもあるため、歯科医師との相談が重要です。
➂経過観察には定期的なチェックが必要
親知らずを残す場合は、レントゲンなどで位置や状態を定期的に確認することが欠かせません。異常があれば早期に対応できるよう、歯科医院での定期検診を継続しましょう。
④患者さんのライフスタイルや治療計画も考慮
受験や就職など、忙しい時期に無理に抜歯するのは避けたほうがよいこともあります。また、矯正治療を検討している場合には、事前に抜歯が必要かどうか判断する必要があります。将来を見据えた上での柔軟な対応が求められます。
5. 名古屋市南区の歯医者 やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療

名古屋市南区の歯医者「やくし歯科・矯正歯科」では、一人ひとりの状態に寄り添い、将来を見据えた治療をご提案しています。
親知らずに関するご相談・診断・抜歯治療も幅広く対応しており、他院紹介や外部医師の派遣ではなく、口腔外科の専門知識を持つ院内医師が対応します。
日々様々な症例に向き合い、丁寧で安心できる診療を心がけています。
また、診断の精度や治療の安全性向上のため、医療機器の導入も積極的に行い、小さなお子さま連れの方でも通いやすいように託児サービスも行っています。
<やくし歯科・矯正歯科の親知らず抜歯治療>
①的確な診断と分かりやすい説明
親知らずは斜めや横向きに生えているケースも多く、抜歯が必要かどうかを見極めるには正確な診断が不可欠です。当院では、高精度なCTやデジタルレントゲンを使用し、親知らずと周囲の神経や血管との位置関係を立体的に把握し、撮影した画像を使いながら、患者さんに分かりやすく丁寧にご説明します。
➁痛みや不安に配慮した麻酔法
抜歯が必要な場合には、局所麻酔や笑気麻酔に加え、眠ったような状態で抜歯治療を行う静脈内鎮静法が選択できます。
➂「抜かない」という選択肢も
すべての親知らずを抜歯する必要があるわけではありません。まっすぐに生えていて問題がなければ、無理に抜歯せず定期的な経過観察を行うケースもあります。患者さんの将来の健康やライフスタイルを考慮し、柔軟な対応を心がけています。
親知らずの治療は、単に「抜く・抜かない」の判断だけではなく、将来の健康を見据えたトータルな視点が必要です。
まとめ
親知らずは、症状がなくても思わぬトラブルを引き起こすことがあります。早い段階で状態を把握し、必要であれば適切な時期に抜歯することで、将来的なむし歯や歯並びの乱れを防ぐことが期待できます。また、抜歯後の過ごし方にも注意することで、治癒がスムーズに進む可能性が高まります。
名古屋市南区で親知らずの抜歯についてお悩みの方は、やくし歯科・矯正歯科までお問い合わせください。
監修:やくし歯科・矯正歯科 院長 鬼頭 広章
所属学会
国際インプラント学会 ICOI Fellow
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯周病学会 会員
日本顎咬合学会 会員
日本デジタル矯正歯科学会 会員
日本臨床歯科学会 SJCD 会員
MID-G 理事
名古屋臨床咬合研究会 NOAH 理事
K-Project 会員
取得資格
USC(南カリフォルニア大学)JAPANProgram 卒業 東京SJCDレギュラーコース修了
OSG(矯正アレキサンダータイポドントコース)修了
ITIインプラントコース ベーシック、アドバンス修了
エキスパートハンズオンCAMLOGコース修了
NOBEL BIOCAREサティフィケート多数取得
インビザライン矯正 ベーシックコース修了
5D アドバンスコース修了
2017年 MID-Gレギュラーコース、マニュアルコース受講
矯正LASコース受講
歯周形成外科マイクロアドバンスコース受講
CSTPC受講
2021年 ODGC (矯正診断コース)修了
アライナーオルソドンティクス6デイズコース
明海大学国際インプラント学会認定コース
ハーバード大学歯学部日本CEコース
認定医
日本デジタル矯正歯科学会
日本顎咬合学会

 052-811-1340
052-811-1340